小田急電鉄、東京メトロ、東急不動産の3社は、「新宿駅西口地区開発計画」のうち「A区」について3月25日に新築着工を行ったことを明らかにしました。
小田急電鉄、東京メトロ、東急不動産は、3社が事業主体となる「新宿駅西口地区開発計画」について、3月25日に3社共同事業「A区」にて新築着工したと発表した。2029年度の竣工を目指し、小田急百貨店 新宿本館跡地に48階建て複合施設を建設する。
Impress WATCH
この計画は、新宿駅西口にあった小田急百貨店新宿本館の跡地を活用して、48階建ての複合施設を建設するものです。低層階には商業施設(地下2階〜10階)、高層階にはオフィス(14〜46階)が入居。最上部の47・48階には眺望を活かした空間、体験を提供(展望施設や高層レストランか)、中層階には流行りのビジネス創発機能(12・13階)を導入するとのこと。
ここから私見ですが、ターミナル駅における複合再開発は差別化が難しいものだと思わされます。計画を見る限りでは、既存の渋谷スクランブルスクエアなどと構成がよく似ており、やはり紋切り型の商業施設+オフィスになるのだろうと思わされます。
オフィスでは、東京都心部(山手線東側エリア)での再開発の進展と都心回帰の流れのなか、相対的に新宿を含む副都心エリアの地盤沈下が起きています。商業施設では、郊外型ショッピングセンターが充実し、インターネット通販がさらに競争力を増しています。そうした環境の中で、今回の再開発がどれだけ新宿に付加価値をもたらすのか、正直疑問です。
個人的には渋谷スクランブルスクエアは面白くないと感じており、これが第二スクランブルスクエアになるのだとすれば、また面白くないものができたと感じるに違いありません。渋谷の東急にしても、新宿の小田急にしても、商業フロアはどうでもよくて、オフィス床を高値で賃貸して儲かればよいという考えなのでしょうか。
さすがに規模と立地が違うので、新宿駅新南口のミライナタワー&ニュウマンほど空気にはならないと思います(隣のバスタ新宿が盛況なのと対照的)が、今回の計画地区に隣接するJR東日本と京王電鉄の再開発も含めて、魅力ある商業エリアになるかというと正直疑問です。
さて、儲け話は上層階のオフィスで勝手にやってもらうとして、一般人が気になるのは低層階の商業施設部分です。事業者側の説明や図面からは、JR東日本「ルミネ」や相鉄「ジョイナス」のようなファッションビル(都市型SC)業態となることが読み取れます。これ自体は現代の潮流ですし違和感はありません。
では、この計画の以前にあった「小田急百貨店」の百貨店業態は今後どうするのかということです。渋谷の「東急百貨店」は閉店と言い切って、もう元には戻らない宣言をしているのに対し、小田急百貨店は本館閉鎖時に「(小田急ハルクへ)お引越し」という表現をしており、現在でもハルク内で営業を継続しています。
これまで百貨店業態はオワコンと言われ続けてきましたが、消費の2極化とインバウンド需要で特に大型店の伸びが大きく、三越伊勢丹や高島屋は過去最高の売上、利益を実現しています。小田急が新宿で百貨店を続けるのかどうかは明らかでなく、煮えきらない態度を取り続けているのもこうした百貨店業界の「再興」が背景にあると思われます。
この計画のうち今回着工した「A区」の南側で小田急電鉄が単独で計画する「B区」の詳細がまだ明らかになっていませんが、この商業床は新生・小田急百貨店になるのではないかと筆者はひそかに思っています。狭い小田急ハルク内だけで営業を継続するのは無理がありますし、なにより既存顧客からの突き上げに耐えられない、もう顧客を繋ぎ止めるのに限界がきているものと推察されるからです。
いまや、ほとんどのモノはインターネットで買えるようになり、また都心部の商業ビルに入居するテナントの多くは郊外のショッピングセンターにも入居して品揃えがほとんど変わらなくなり、わざわざ都心部に足を運ぶだけの理由が薄れてきています。そんな中でも、都心部でしか手に入らないものを提供してくれるのが百貨店という業態ではないでしょうか。チェーンストアやネットショッピングとは違う対面販売という体験価値、普通の店とは一味違う高感度な商品群は百貨店でなければ得られないものだと思います。小田急が本当に新鮮な購買体験を提供したいと思うのであればこそ、百貨店業態に立ち戻るべきではないでしょうか。小田急百貨店の跡地に小田急百貨店が戻ってくることを切に願います。
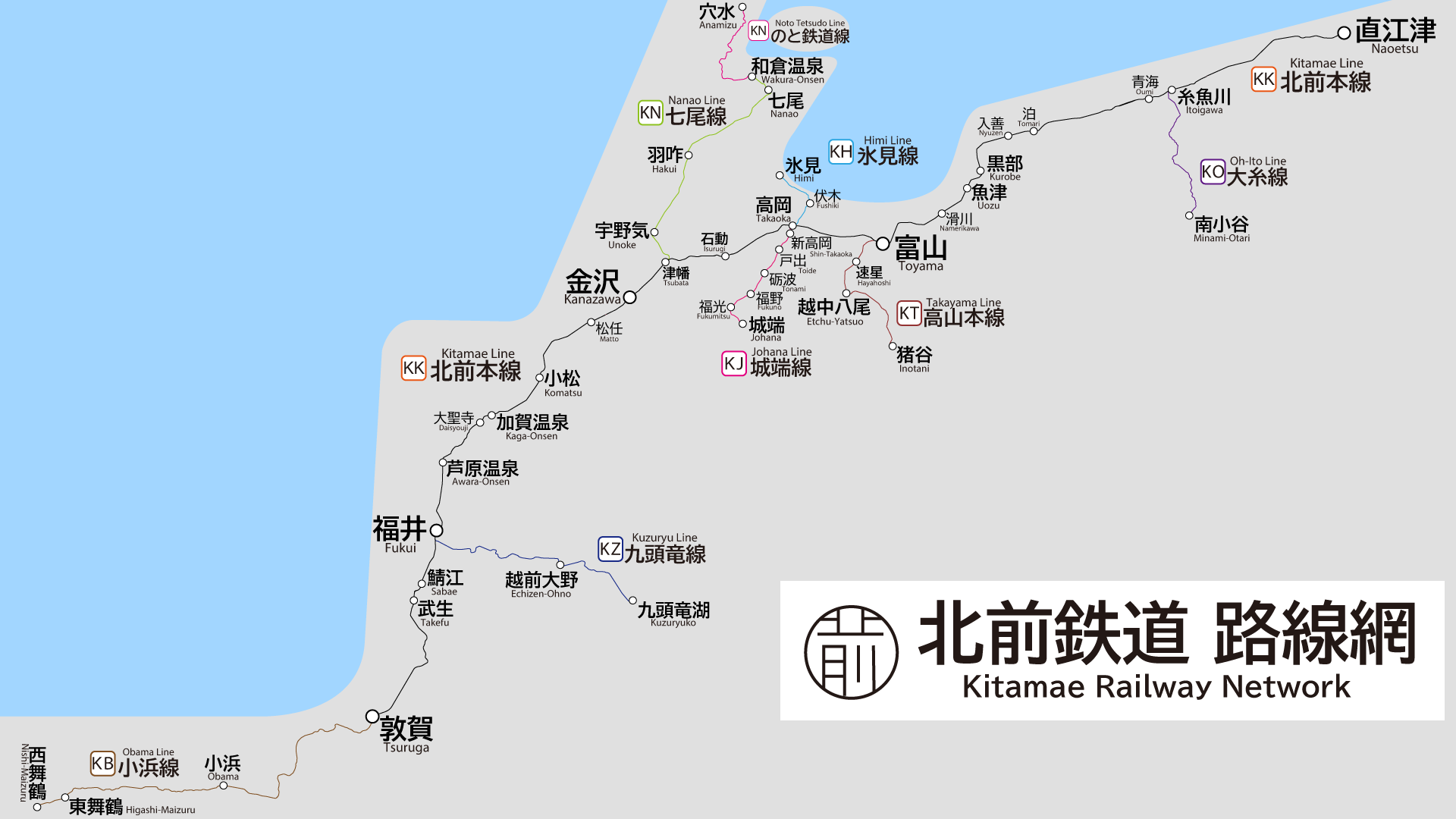
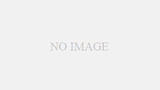
コメント